\ 公式LINE登録は完全無料 /
今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

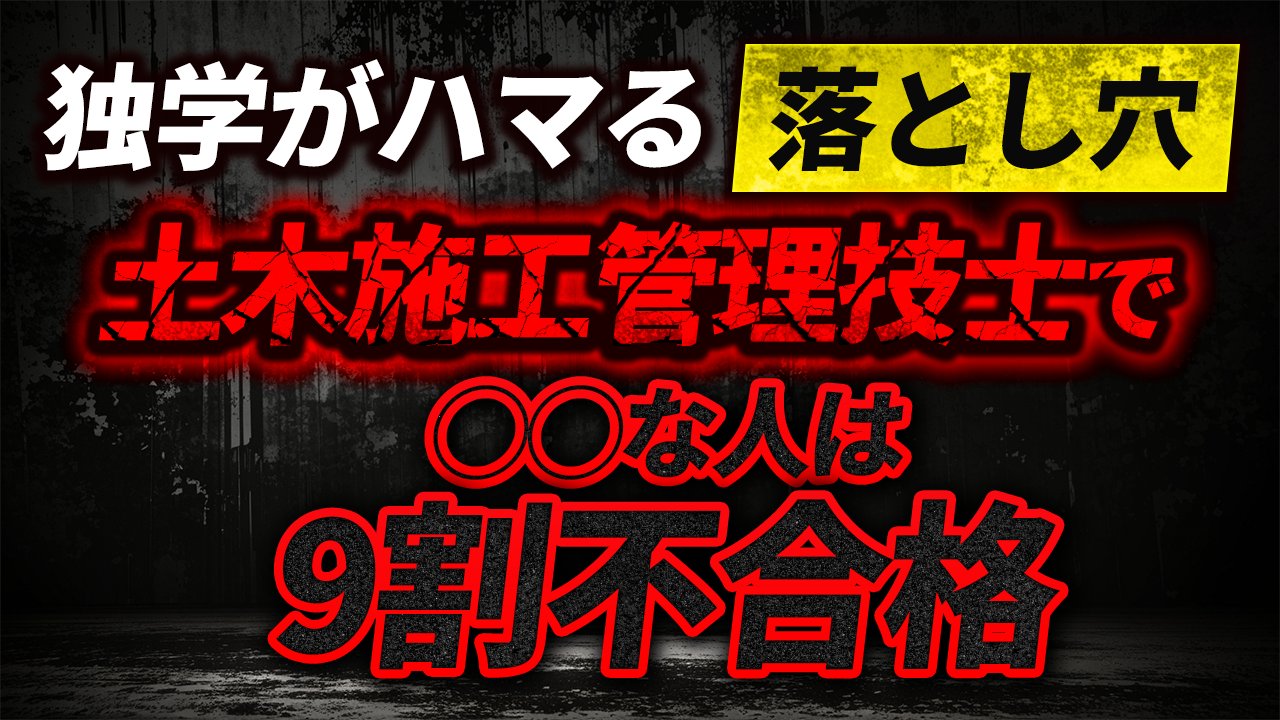
「土木施工管理技士の試験、独学で受かるのだろうか…」
「参考書を最初から読んでるけど、この勉強法で本当にいいの?」
「仕事が忙しくて時間が取れない。でもスクールに通う余裕もない…」
本記事はこんな悩みを持つ方へ書いた記事です。
この悩みや不安、私も痛いほどよくわかります。
結論から言うと、独学でも合格は可能です。ただし、やり方を間違えると、努力が水の泡になります。
かつての私も、同じように参考書を1ページ目から読み進め、努力しているつもりなのに手ごたえがなく、「このままで本当に大丈夫か?」と焦っていました。
この記事では、独学で合格を目指すあなたに向けて、「絶対にやってはいけない勉強法」と「合格に直結する最短ルート」を、実体験をもとにわかりやすく解説しています。
遠回りせず、限られた時間で最短合格を目指したい方こそ、ぜひ最後までご覧ください。
・【体験談あり】試験勉強に潜む落とし穴
・合格がグッと近づく4つの勉強のコツ
・第一次検定・第二次検定に対しておすすめの参考書
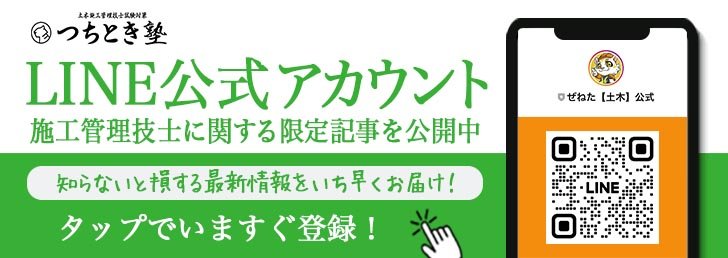

 ぜねた
ぜねた結論から言うと、参考書の1ページ目から勉強し始める人は合格できません。
その理由は、勉強する必要のない部分に時間が取られてしまうから。
参考書の最初から勉強すると、時間がいくらあっても足りません。
これ、勉強しようとする人が陥る間違いなんです。かくいう私もこの落とし穴に見事にハマりました。
 ぜねた
ぜねた土木施工管理技士の試験ではないですが、私もコンクリート技士の試験を受ける際に、この落とし穴に見事にハマりました。
参考書を最初から読み、知識を増やしていきました。 (でも、実は増えた気になっているだけ…)
約1ヶ月程度ですかね。
ほぼ毎日1時間、参考書をはじめから読み進め、勉強していました。
「これはいけるぞ」と謎の自信を持って、いざ1週間前に過去問を解いても全然わからない・・
まぁ、結果、不合格でした。
その失敗を踏まえて、土木施工管理の試験では”過去問中心の勉強方法”に変えることで、無事に1発で合格です。
また、建設会社で働いていた同期の中で、土木施工管理技士の試験に落ちていた人は、 「全然勉強していない人」か 「参考書から勉強をしていた人」のどちらかでした。
参考書を読んでインプットをしていると、参考書を読んで勉強している気にはなるのですが、本当の実力がついているかどうかは怪しいです。この方法はおすすめしません。
では、合格するためにどうやって勉強をしていけばいいのか。
その方法を詳しく解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。

土木施工管理技士の試験に合格するために、絶対に欠かせない“たった一つのこと”。
それは、「心構え(マインドセット)」です。
「心構え」と聞くと少し抽象的に感じるかもしれません。
ですが、簡単に言えば「どんな考え方で試験に臨むか」ということです。
もっと率直に言えば、「絶対に合格してやる」という強い覚悟のことです。
なぜこの心構えが重要なのか?
 ぜねた
ぜねたそれは、マインドが整っていないと、どんなに良い勉強法を知っていても、それを「実行」できず、「継続」もできないからです。
試験勉強では、正しい方法を知るだけでなく、それを地道に積み上げていく力が求められます。
つまり、「やる気」と「続ける力」は、しっかりとしたマインドがあってこそ生まれるのです。
私自身、試験に向けて取り組む中でこのことを痛感しました。
逆に、この気持ちが欠けているとどうなるか?
私の同期で、3年連続で不合格になった人がいました。
彼は「どうせ無理だろう」とどこか他人事で、試験前日にもパチンコに行っていたそうです。気持ちが定まっていない状態では、当然ながら行動にも身が入りません。
まずは、「何が何でも合格する」という強い気持ちを持つこと。それがすべての出発点になります。
この内容を以下の動画でも解説しています。この動画を参考にして、強い合格に向けて強い気持ちを持って下さい。

土木施工管理技士の合格を目指すための勉強方法は以下のとおりです。
合格が近づく4つのコツ
・やらないことを決める
・インプットとアウトプットの割合を意識する
・合格から逆算して勉強する
・第三者の力を借りる
このうち、 前半の2つが勉強のための準備で、 後半の2つが勉強の方法です。
詳しく解説します。
 ぜねた
ぜねた試験勉強を進めるうえで、最も大切なのは、実は「何をやるか」ではなく、「何をやらないか」を明確にすることです。
なぜ、やらないことを決める必要があるのでしょうか?
その理由はシンプルで、「やめることを決めない限り、新しい時間は生まれない」からです。
特に、現場監督や施工管理の仕事に従事している方であれば、「勉強したいけれど、そもそも時間がない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
日中は工事現場に立ちっぱなしで作業や管理に追われ、夕方からは事務所で書類業務。そんな過密なスケジュールのなかで、勉強時間を確保するのは至難のワザです。
このような状況で、ただ漠然と「時間を作らなければ」と思っても現実は変わりません。
本当に勉強時間を生み出したいのであれば、まずは今の生活や仕事の中で「やめられること」「削れること」を見つけ、意識的に手放していく必要があります。
合格の第一歩は、「やることを増やす」よりも、「やめることを決める」ことから始まります。
やめることを決めないと、いつまでたっても時間はできません。
私は日々の生活を見つめなおし、以下の内容をやらないと決めました。
試験までは、この2つを絶対にやらないと決めました。 そして、 「その時間を勉強にあてる」
と決めて、時間を作りました。
時間の確保
・平日1時間
・休日3時間
月~土で5日、日曜日3時間とすると、1週間で8時間とれます。
 ぜねた
ぜねたこれを4週間続けたとすると、約30時間です。
第一次検定についても、最低限これくらいの時間は確保しましょう。
土木施工管理技士の試験は、「選択式」や「記述式」といった形式にかかわらず、最終的には“アウトプット=自分の知識を外に出す力”が問われる試験です。
つまり、本番で求められるのは「覚えていること」ではなく、「使える知識かどうか」です。
このことを踏まえると、試験勉強でもアウトプットを重視する必要があります。
たとえば、参考書を読むだけの学習は「インプット」に過ぎません。
知識を頭に入れる段階ではありますが、それだけでは試験で点を取る力にはつながりにくいのです。
 ぜねた
ぜねたもちろん、学習の初期段階ではインプット中心でも構いません。
しかし、試験日が近づくにつれて、インプットの比率を下げ、アウトプット、つまり「問題を解く」「記述を書く」「声に出して説明する」といった実践的な学習の割合を増やしていくことが、合格に向けた近道です。
インプットとアウトプットの比率
インプット:アウトプット= 7:3
インプット:アウトプット=1:9
このように、インプットだけで満足せず、「覚えた知識をどう使うか」を意識して、日々の勉強にアウトプットの時間を取り入れていきましょう。
 ぜねた
ぜねた高校生のように、赤マーカーで答えを書いて、赤い下敷きで消す方法も効果的な方法です。
 ぜねた
ぜねた試験に合格するためには、合格から逆算しましょう。
なぜなら、試験勉強というのは、今の自分と合格基準のギャップを埋める行為だから。
試験の合格基準は、第1次検定なら全体の6割、 それに加えて施工管理で6割以上の正解です。
この基準に対して、今の自分には「何が必要」なのか可視化してから、そのギャップを埋めあるために勉強しましょう。
具体的には、まずは過去問を解いて現状の得点を把握します。そして、合格基準に足りていない部分が何かわかったら、そこを重点的に勉強して下さい。
合格基準の 44点に対して、自分の得点が25点だとすると、足りない19点を獲得できるようにならなくてはいけません。
 ぜねた
ぜねたこのギャップを埋める行為が試験勉強であり、逆算思考です。
土木施工管理技術検定の第二次検定では、自身が関わった工事の経験について記述する「経験記述」の問題が出題されます。この経験記述は、1級・2級に共通して出題されるものであり、受験者の多くが最も苦戦する“最大の関門”といっても過言ではありません。
とはいえ、この問題にもある程度の出題傾向があるため、あらかじめ準備することが可能です。
そのため、多くの受験者は事前に作文を作成し、試験当日はその内容を思い出しながら、多少のアレンジを加えて解答しています。
令和6年度から試験問題に変更がありました
ここで最も重要になるのが、「事前に準備した作文のクオリティ」です。
いくら当日、その作文を再現できたとしても、その内容自体が合格基準を満たしていなければ、当然ながら合格にはつながりません。
つまり、試験に向けた準備の段階で、合格基準に達するレベルの作文を用意しておくことが不可欠なのです。
では、どうすれば“合格できる品質”の作文を事前に用意できるのでしょうか?
ここで大切なのが、「第三者の視点」です。
なぜなら、作文を評価するのは、 試験管である第三者であるから。
いくら本人が合格基準に達していると思っていても、 第三者には伝わらないなんてこともあります。
 ぜねた
ぜねた実際に、私は同じ現場の先輩に添削いただいたことに加えて、 自分が勤務する会社が用意してくれた添削サービスを利用しました。
そこで、作文をブラッシュアップできたからこそ、合格することができたと言い切れます。
事前に準備をした作文は必ず第三者に見てもらいましょう。
なお、経験記述の書き方については、以下の記事で詳しく解説しています。
1.8万字の大ボリュームで、書き方の基本からすべて解説しているので、 これ1記事で経験記述は網羅できます。
 ぜねた
ぜねた書き方を0から学びたい方や、 試験に合格したい方は、ぜひ読んでください。
✅経験記述完全攻略


「どの参考書で勉強すればいいの?」と気になる方のために、第一次検定、第二次検定に分けておすすめの参考書を紹介します。
①第一次検定対策
1.令和7年度版土木施工管理技士第一次検定出題分類別問題集1級
2.1級土木施工管理第一次検定問題解説集2025年版
3. CIC 出版 1級土木施工管理技士 第一次検定テキスト
②第二次検定対策
1. 2025 年版 1級土木施工第2次検定徹底解説テキスト&問題集
2. 土木施工管理第二次検定問題解説集
3. プロが教える1級土木施工管理技士第二次検定
1.令和7年度版土木施工管理技士第一次検定出題分類別問題集1級
令和7年度版土木施工管理技士第一次検定出題分類別問題集 1級は、過去問を中心とした参考書です。
内容は、過去問と解説がセットになっているので、基本の繰り返し使える参考書です。
図解による解説が豊富で、視覚的にわかりやすく理解が進みます。
 ぜねた
ぜねた試験の解説だけでなく、試験によく出る重要項目の解説もなされているので、非常に使いやすいです
2. 1級土木施工管理第一次検定問題解説集2025年版
1級土木施工管理第一次検定問題解説集2025年版は、過去問を中心とした参考書です。
過去7年分の問題が記載されており、その全てに、「なぜ誤っているのか」「どうして正しいのか」を図解を使って詳細に解説してあります。
 ぜねた
ぜねた白黒のテキストなので、マーカーなどで記載すると目立って見やすいです。
3. CIC 出版 1級土木施工管理技士 第一次検定テキスト
この書籍は、過去問の解説は一切入っておらず、参考書として利用できるテキストです。
無駄なく効率的に勉強を進めるために作成されたテキストであり、過去問を参考に必要な情報が厳選されています。
さらに、書籍の左右に、 「用語解説」 「補足」「頻出」といった項目が書かれたスペースがあり、理解が難しい部分でも、理解しやすいように工夫されています。
1.2025 年版 1級土木施工第2次検定徹底解説テキスト&問題集
土木施工管理技術検定試験研究会の著書で、第2次検定に特化した内容です。
令和6年度の試験から、出題形式が変更された経験記述問題について、最新の情報を反映し、38の工事で、76 もの記述例を掲載されています。
 ぜねた
ぜねた圧倒的な数の例文が掲載されているので、 自分が経験した現場の参考になる例文が見つかります
2.土木施工管理第二次検定問題解説集
昭和40年に当時の建設省から財団法人として認可を受けた地域開発研究所が発行する第二次検定に特化したテキストです。
過去10年分に出題された問題を分野別かつ年度別に編集し、解説しています。
 ぜねた
ぜねた経験記述については、令和6年度の見直しを含めて最新の情報に更新されており、第二次検定に対応するために必要な知識を身に付けるのにぴったりの参考書です。
3. プロが教える1級土木施工管理技士第二次検定
チャンネル登録者数3万名以上のYoutuber ひげごろ一先生の著書です。
令和6年度以前の問題形式ですが、とてもわかりやすく書籍なので、紹介させていただきました。
 ぜねた
ぜねた経験記述から、穴埋め、記述式など、第二次検定の対策に必要なことが1冊で網羅できます。
※試験内容・教科書の内容は見直されることがあるので、参考書は最新年度のものがないか確認してください。
この記事でお伝えした勉強法を試せば、経験記述の対策もバッチリなはずです。また、ぜねた公式LINEでプレゼントしている限定記事も活用して、ぜひ合格を勝ち取って下さいね。
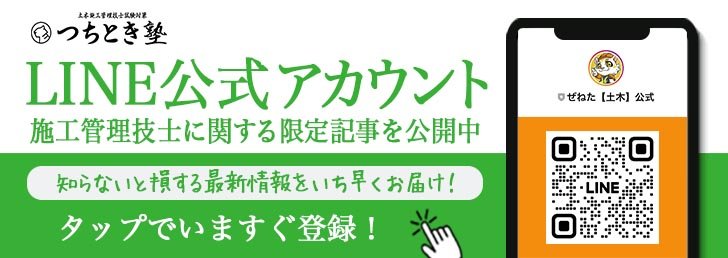
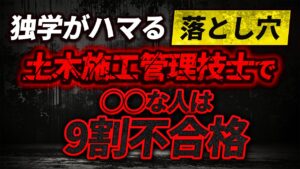
この記事が気に入ったら
フォローしてね!