\ 公式LINE登録は完全無料 /
今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中
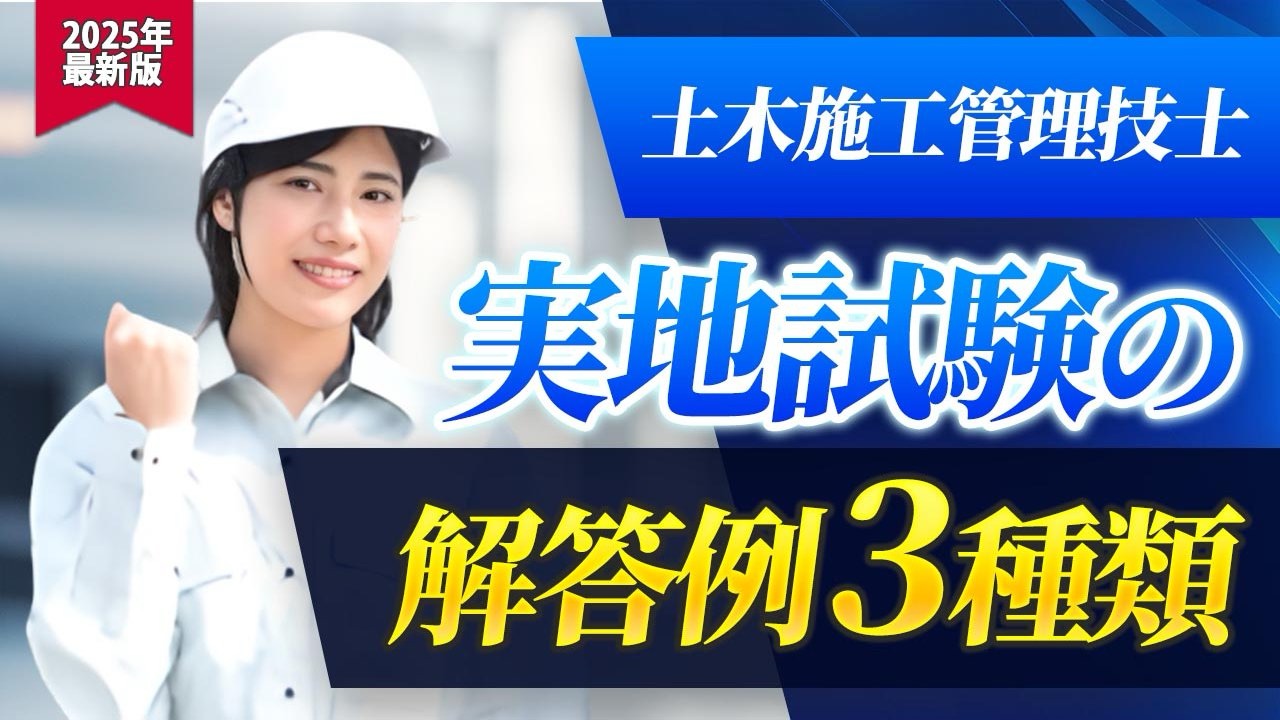
 若手技術者
若手技術者1級土木施工管理技士の実地試験の対策をしたいです
 ぜねた
ぜねた実地試験は経験記述がカギですね
 若手技術者
若手技術者話はよく聞きますが、経験記述が全然書けません
 ぜねた
ぜねた書き方にコツがありますし、試験には明確な傾向があるので、しっかりと準備して臨みましょう
・記述論文に何を書けばいいのかわからない
・実際に合格した人が書いた例文が知りたい
・どういう風に勉強すればいいかわからない
 若手技術者
若手技術者土木施工管理技士の試験で、経験記述にどんなことを書けばいいのかわからない・・・
 若手技術者
若手技術者経験記述の準備をしたいけど、参考にする作文がしりたい・・・
 若手技術者
若手技術者試験問題が変わった時いて、最新の例文が知りたい・・・
本記事では、こんな悩みを解決します。
・令和7年度最新版の経験記述の例文3種類
・合格がグッと近づく記述のポイント
・経験記述の注意点3選
・最短で合格するための勉強方法 【実体験付き】
国家資格である土木施工管理技士の資格を取得するために、鬼門となるのが、第二次検定(旧実地試験)における経験記述の作文問題です。
 ぜねた
ぜねたこの記事では最短で合格するため、令和7年度最新の勉強方法について、 過去問を元に徹底的に解説しています。
そのため、この記事を読み終えれば
「ここまで書けば合格するのか」 という
合格するためのポイントを押さえることができると同時に、
「これなら書けそう」 という手ごたえを感じるだけでなく、
「こうやって勉強すればいいんだ」と合格に至るまでの勉強方法が明確になります。
執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版
仕事をしながら一級土木施工管理技士の勉強をするのは非常に大変だとは思うので、この記事で必要な情報だけ集めて効率的に勉強してください。
参考書とは違い個人のブログではあるからこそ、具体的な体験談も交えて解説しました。
ぜひ、最後まで読んで合格を勝ち取りましょう。
なお、本記事では1級土木施工管理技士の経験記述の論文に対して例文を交えて解説していますが、注意点を先に共有します。
当サイトで紹介した論文の丸写しはNG
丸写しや丸パクリは絶対に、バレるのでやめてください。
そんなことをする人はいないとは思いますが、よろしくお願いします。
ちなみに、土木施工管理技士の問題でよく聞くのが「第二次検定の配点ってどうなってるの?」という質問です。
[1級・2級土木施工管理技士の実地試験(第二次検定) における配点とは? 合格への最短距離]という記事で、配点について詳しく解説しています。


最新の経験記述作文における例文を2つ紹介します。
まずは例文を読んで、「これくらい書けば合格できるのか」と、合格の基準を理解しましょう。
当サイトで紹介した作文の丸写しはNG
安全管理上の課題に対する解答例を紹介します。
解答例)
本工事は、1日の乗降者数5万人を超える○○駅に面した道路を、延長 500mにわたり切削オーバーレイにより補修を行う工事であった。当該工事路線は幅員 5.5mであり、作業帯2.5m を確保すると車両の通行帯が3.0m と狭隘であることに加えて、駅前であることから通勤・通学として多くの歩行者が利用する道路であった。そのため、歩行者及び車両等と重機の接触事故防止が課題であった。安全に留意するため、以下の3点について、 検討を行った①歩行者の安全を確保について、駅前の工事であり歩行者が多いことから、歩行者の安全を確保するための検討をした。②ヒューマンエラーの防止として、作業員や重機オペレータ一の不注意を防止するため、見張り員の配置を検討した。③周辺住民への広報として、通行車両及び歩行者への工事内容を周知させるための広報活動の検討をした。
解答例)
検討結果について、本工事では以下の処置を行った。①歩行者の通行帯として車道と完全に分離し、2mの幅員を確保するとともに段差解消のマットを設置した。また、駅前であることから、仮設の点字マットを10mにわたって設置した。②歩車道を完全に分離するため単管バリケードにより仮囲い 30m 設置。さらに超小旋回型の重機を使用しダンプによる土砂運搬を行う際には、見張り員を設置した③工事着手 1ヵ月前に工事説明会を行い、さらに工事看板を3週間前に工事区域の50m手前から設置した。以上の結果、事故なく工事は無事に完成した。事故なく工事を完了できたことから、今回の対応については安全管理に有効な対策だったと評価できる。
当サイトで紹介した作文の丸写しはNG
品質管理上の課題に対する解答例を紹介します。
解答例)
本工事は、◯◯県内の〇〇川流域の左岸において延長 O0mにわたり築堤を構築する工事であった。盛土材料は、近隣のトンネル工事で発生した岩ズリを使用する予定であった材料のストックヤードに出向いたところ、粒径のバラつきが大きく、含水比が高かったため締固めが均一にならないことが懸念された。 そのため、所要の締固め度 (90%以上) を確保することが技術的課題であり、締固め度を確保するため、以下の検討を行った。 ①転圧方法については、岩ズリは粒径が大きいことに加えて、材料のバラつきが大きいため、工法規定方式の検討 ② 岩ズリの大きさについては、材料のバラつきにより、大割れした岩ズリが多く散見されたため、岩ズリの粒度調整について検討した。数種類の試験盛土を行い、 転圧機種、敷き均し厚み、 転圧回数、 転圧機械の速度を検討した。
解答例)
本工事では以下の処置を行った。①岩ズリについて、数種類の試験盛土を行い、 転圧機種、 敷き均し厚み、 転圧回数、 転圧機械の速度を検討した。その結果、 転圧機械をタイヤローラ (8~20t級) 1層の厚み:300cm、転圧回数:〇回、 機械の速度: ◯◯km/h とし、 工法規定により品質管理を行った。②0.7㎡ 級のバックホウにスケルトンバケットを装着し、 骨材をふるいわけを行った。そして、オーバーサイズの岩ズリは破砕機で破砕し 最大粒径を40mmの盛土材料とした。以上のことにより、所要の締固め度 90%以上を確保することができた。 岩ズリを使用しながら、所定の締固め度を確保できたため、品質管理に有効な対策であったと評価できる。
令和6年度から、問題1は設問が2つになりました。
実際の設問は、以下のとおりです。
〔設問2〕 工事概要に記述した工事の施工計画の作成に関し、次の事項について解答欄に具体的に記述しなさい。 ただし、設問と同一内容の解答は不可とする。
(1) 施工計画立案に先立ち行った現場の事前調査で判明した施工上の課題
(2) (1)で記述した課題について施工計画の作成にあたり反映した対応処置とその評価
この問題に対する解答として、ポイントや例文を解説します。
 ぜねた
ぜねた令和6年度における解答のポイントは、 事前調査で判明した課題に対する解答であることでした。
現場の課題というのは、施工をしてみてわかることもあります。
例えば、 設計図書ではGH-5mで支持地盤となっていたが、 実際に掘ってみると5mでも支持地盤ではなかったといったこともあります。
しかし、今回の解答としては、施工計画の立案時であるため、契約時から判明していた技術的な課題に答える問題でした。
例えば、
・現場の自然的な条件 (現場が急峻な山奥、 渇水期のみ施工可能、工事現場が駅前など)
・社会的な条件(終電後に施工可能、施工時期が夏冬、 資機材搬入ルートが通学路など)
事前に用意していた 「安全管理」「品質管理」「工程管理」について、 施工計画立案時にわかっていた課題や対応策を記述すれば解答できました。
先ほどの解説を踏まえて、解答例を紹介します。
例として、先ほどの安全管理で解答した道路工事を例にして解説します。
(1) 施工計画立案に先立ち行った現場の事前調査で判明した施工上の課題
解答例)
本工事は、1日の乗降者数5万人を超える○○駅に面した道路を、延長 500mにわたり切削オーバーレイにより補修を行う工事であった。当該工事場所は、駅前であることから通勤・通学として多くの歩行者が利用する道路であった。当該工事は、施工計画を立案する上で、以下の3点において検討を行った。当該工事路線は幅員 5.5m であり、作業帯2.5m を確保すると車両の通行帯が3.0mと狭隘であることに加えて、駅前であることから通勤・通学として多くの歩行者が利用する道路であった。そのため、歩行者及び車両等と重機の接触事故防止が課題であった。 安全に留意するため、以下の3点について、検討を行った①歩行者の安全を確保について、駅前の工事であり歩行者が多いことから、歩行者の安全を確保するための検討をした。②ヒューマンエラーの防止として、 作業員や重機オペレーターの不注意を防止するため、見張り員の配置を検討した。③周辺住民への広報として、通行車両及び歩行者へ工事内容を周知させるための広報活動の検討をした。
(2)(1)で記述した課題について施工計画の作成にあたり反映した対応処置とその評価
解答例)施工計画を立案する上で、以下の3点において検討を行った。①作業箇所は日陰になる場所がないことから、休憩所としてクーラーの聞いた休憩車を設置し、吸水ボトルと塩分タブレットを常備した。②作業当日の体調が大きく影響することから作業開始前のKY時に職長が全作業員の顔色を確認し、KY用紙に記入し、異常がないかの確認を行った。③安全教育時に、熱中症の危険性と防止策に関する教育を実施し、周知を行った。 以上の対策を実施したことにより、熱中症を発生させることなく無事に工事はしゅん工した。 熱中症の発生を0にすることができたことから、これらの対策は効果があったと評価できる。
令和6年度に新たに出題された設問について、解答例を解説しました。
例文や解答例を示したので、次に基本的な書き方について解説します。
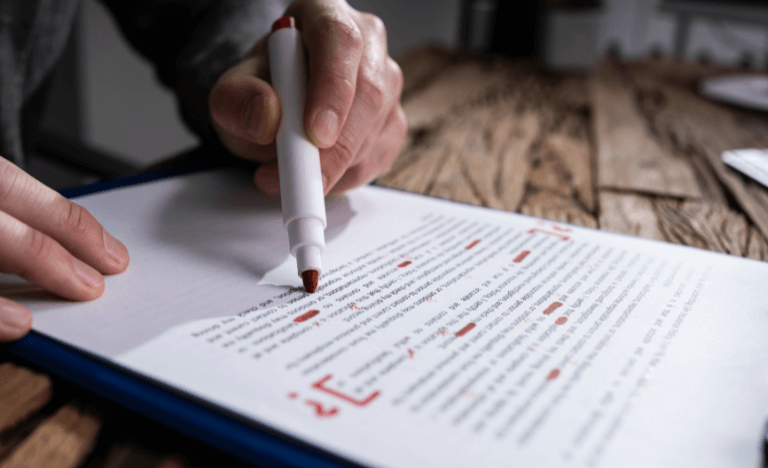
 若手技術者
若手技術者経験記述のポイントを教えてください
 ぜねた
ぜねた事前の準備が9割です。まずは、傾向を捉えてしっかりと対策を取りましょう
施工経験記述の目的は、 施工管理技士にふさわしい技術者であるかどうかを判断することです。
工学的な知見に基づく適切な判断と、 施工管理技士としてふさわしい経験を有しているかどうかを評価します。
 ぜねた
ぜねた逆にいえば、高度な技術や最先端の知見を求めているわけではないです
では、どのように判断されるのかというと、「現場でどのように創意工夫をしたのか」を求められます。
経験記述における基本的な注意点は以下の通りです。
・長い文章は避ける
・箇条書きを活用する
・「です・ます」 調を避けて、 「である」調にする
・誤字・脱字に注意 (わからない場合は漢字を間違えるより “ひらがな “で)
いきなり、論文の作成例を紹介する前に、工事件名など必須の内容を簡単に解説します。
そんなの知ってるよ。って方は読み飛ばして頂いてOKです。
工事の対象や場所、 種類が分かるように工事件名を記載します。
市道〇〇号線道路補修工事
〇〇川災害復旧工事
国道○○号線○○工区道路改良工事
新東名高速道路〇〇橋下部工工事
受験申し込み時に書いた工事名とおり、正式な工事名を記載します。
 ぜねた
ぜねたちなみに、「道路工事」 「護岸工事」 など単なる工事の名称だけはNGです。
採点者が見るべきポイント
本当に工事が存在するか
土木の工事かどうか
本当に存在する工事なのか採点者は判断できません。
そのため、工事名を見ただけでどんな工事かイメージできるように、工事名は正式名称でわかりやすく書きましょう。
また、土木の工事か判定しにくいような工事は注意が必要で、なるべく規模が大きい公共工事を選ぶ方が無難です。
①発注者
○○市、国土交通省○○○事務所、 ○ 日本高速道路株式会社、 ○○建設株式会社
元請けとして、発注者から直接工事を請け負った場合、発注者名をそのまま記載します。
 ぜねた
ぜねた下請けととして入った場合は、自分の会社に発注した会社を記載しましょう。
②工事場所
○○市○○町○○番先
○○市○○町○○丁目○○番~〇〇番先
市または、郡で終わるのではなく、なるべく詳しく記載しましょう。
③ 工期
令和〇年〇月〇日 ~ 令和○年○月○日
正確に元号の年から日付まで記載すること。
工期が短いのに工種や数量が多いとか、 逆に、工期が短いのに工種や数量が少ないと違和感が生じるので注意が必要です。
④主な工種
切土工、盛土工、路床工、路盤工
橋台工、橋脚工、深礎杭
山岳トンネル工、 掘削工、 インバート工、覆工
工事の内容がイメージできるように、 主な工種を記載します。
代表的な工種だけでOKです。
 ぜねた
ぜねた全部記載する必要はありません。
⑤ 施工量
主な工種に記載した工種に対応するように、 構造物の規模や施工数量 (m、㎡’, m’、 本、個)を具体的に記載します。掘削土〇〇㎡、車両防護柵○m、コンクリート 〇〇㎡、橋脚○基、重力式擁壁工◯m
書ける場合は、さらに具体的に書くと現場状況がわかりやすくなります。
コンクリート (18-8-20BB) ◯◯㎡
重力式擁壁(H=2.5m)◯m
ここまではやらなくても大丈夫ですが、工事に対して信ぴょう性が高まりますし、なにより具体的にイメージできます。
さらに、 経験記述の際により伝わりやすくなるので、できる方は記述してみることをオススメします。
工事現場におけるあなたの立場を記載します。
工事係、 工事主任、 現場代理人、 監理技術者、 発注者側監督員
 ぜねた
ぜねた施工管理技士の試験なので、基本的には施工を管理した役職を記載しましょう。
具体的な現場状況と特に留意した技術的課題とその課題を解決するために検討した項目ですが、大きく2つに分けて考えましょう。
・現場状況と技術的課題
・課題を解決するために検討した項目
まず、1つ目の「現場状況と技術的課題」ですが、以下のように細分化して考えます。
①工事の概要及び事業全体の概要や目的
②課題が生じた背景 (現場の状況)
③解決すべき技術的課題
まずは、この内容で工事内容と技術的な課題を整理して、書き出してみましょう。
注意点としては、 具体的な内容を記述すること
具体的な例
・地名、名称
・寸法、面積、延長、 数量
・特有の地質、気象など環境条件
技術的な課題は1つに絞り、 数値を用いて記載します。
例文は、以下の通りです。
具体例
① 工事の概要
本工事は○県における○○地区〇〇整備事業の1工区として新しく道路(W=Om、L=00m)を構築するものであった。
② 課題が生じた背景 (現場の状況)
工事期間が冬季にわたり、現場周辺の12月~2月の過去10年の気象データを集計すると、日平均気温が4℃以下となる日は12月下旬から2月上旬にわたって 35 日程度で、 最低気温は-5℃。
街渠工のエプロンコンクリートの打設が寒中コンクリートによる施工となる計画であった。
③解決すべき技術的課題
従って、厳寒期におけるコンクリートの品質管理が重要な課題であった。
工事の概要課題が生じた背景 (現場の状況) 解決すべき技術的課題という流れで構成すると、わかりやすくまとまります。
注意点は以下の通りです。
①対処方法まで記載しないこと
②技術的な課題の原因が、 自社の施工不良と捉えられないように注意
具体的に詳しく解説します。
①対処方法まで記載しない
「具体的な現場業況と特に留意した技術的課題」 で求められているのは、解決すべき技術的課題が何かということ。
「対処方法」 まで記載している事例があります。
 ぜねた
ぜねた同僚の作文を添削すると、たまに見受けられます。
対処方法は別の欄に記載するので、 記述をきちんと分けましょう。
② 技術的な課題の原因が、 自社の施工不良と捉えられないように注意
技術的な課題が生じた背景や原因は、気象条件や、 発注者の都合など、第三者や天災が適しています。
自分の会社の力ではどうしようもないような課題を、技術的に解決した例を記述しましょう。
例
集中豪雨により、のり面の崩壊
設計と異なる地質の変化
地元との協議の遅延による工程の遅延
 ぜねた
ぜねた①、②などを使用して記述するとわかりやすくなります。
書き方の例
理由+検討項目
①○○だから、○○を検討。 ②○○だから(技術的な課題を背景とした懸念点) ○○を検討
検討内容は、理由+検討項目の記載が望ましいです。
なぜなら、技術的な課題とのつながりが明確になるから。
検討した項目は、あくまで技術的な課題を背景としなければなりません。
理由はなくてもいいかもしれませんが、書いた方が技術的な課題との繋がりが明確になります。
文字数が多すぎる場合は削っても OK
例
技術的課題: 第三者災害の防止
歩行者の安全を確保について、 駅前の工事であり歩行者が多いことから、 歩行者の安全を確保するための検討をした。
歩行者の安全を確保について、駅前の工事であり歩行者が多いことから→理由
歩行者の安全を確保するための検討をした→検討項目
技術者として自分自身の経験に基づき、 どんな技術的な背景に基づけ、 なぜその項目を検討し、わかるように記述しましょう。
技術的な課題及び、検討した項目を踏まえて、実施した対応策を具体的に記述します。
工法、 機械、 作業日数等について、 数字を交えてできるだけ詳しく記述しましょう。
上述した 「検討した項目と検討理由及び検討内容」 について箇条書きした場合は、番号を関連させた対処方法を記述します。
 ぜねた
ぜねた成果を数字で表すことができると、 具体性を感じる記述になります。
例
○t 級の施工機械を○台増やしたことで、○日工期の短縮することができ、 工期内に無事に工事が完了した。
そして、最後に評価です。
対応処置をおこなったことにより、問題のテーマ (安全管理など) を達成できたので有効な対策だったと評価できる
といった構成です。
定型文のようなものなので、以下の例文を参考に覚えちゃいましょう。
例
以上より、○○(技術的課題)を「防ぐ・発生させる」ことなく、○○(理想の状態)「できた・なった」ことは、品質確保に有効な対策だったと評価できる
以上より、 〇〇 (対応処置) の処置を行ったことで、事故なく安全に工事を完了できたことは、安全管理上、 有効な対策だったと評価できる
以上で、基本的な書き方の解説を終了です。

土木施工管理の技術検定において、経験記述を書く上での注意点を紹介します。
とはいえ、それほど難しいものではなく、 基本中の基本と言っていい内容です。
 ぜねた
ぜねた逆に、これを知らないと合格が遠ざかってしまうので、初めて経験記述を書く人は、必ず読んでくださいね。
経験記述を書く際には、以下の3つのポイントに注意してください。
・「です・ます」 調を避けて、「である」 調にする
・長い文章は避ける
・誤字・脱字に注意 (わからない場合は漢字を間違えるより “ひらがな “で)
基本的に、「です」「ます」 調ではなく、「である」 調で記述します。
その理由は、です」「ます」調の方が、説得力がある文章になるからです。書籍や、ネット上にある例文を読んでもらうとわかるのですが、必ず「である」調で書いています。
また、一文は短く書きましょう。なぜなら、 短い文章ほど伝わりやすいから。
採点者はあくまで人です。 そのため、採点者が理解できる文章でないと、合格はできません。しかし、長い文章だと何を言いたいのか伝わりにくい場合があります。 そのため、長くても100字までに押さえましょう。
最後に、基本的に作文では専門用語を使って構いませんが、誤字・脱字に注意してください。
専門用語を使った方が良い理由としては、採点者に「この人は技術者として専門性がある人だ」と思ってもらいやすいからです。
 ぜねた
ぜねたですが、当日、漢字が思い出せないこともあると思います。そんな時は、ひらがなで書いても大丈夫なので、諦めずに落ち着きましょう。
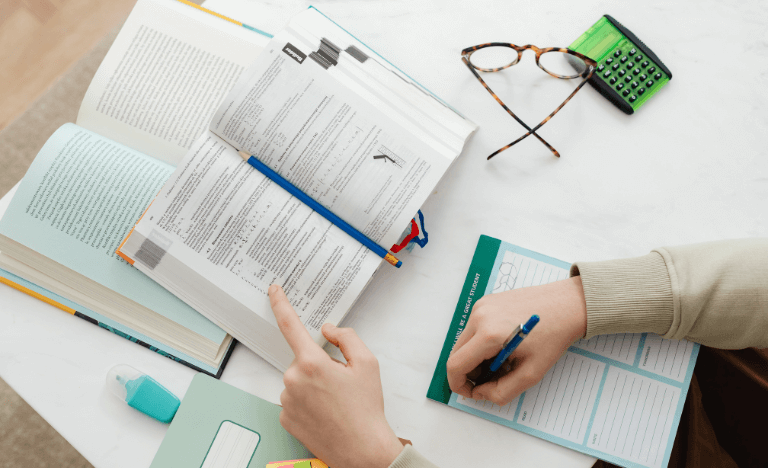
私が1回の受験で合格するために行った勉強方法は、とにかく経験記述を繰り返し何度も書いて覚えたことです。
しかし、クオリティの低い文書をいくら書いても合格にはつながりません。
そこで、大切なのは第三者からフィードバックをもらい、文章をプラッシュアップすること。
これが合格への最短経路です。
 ぜねた
ぜねた私も論文を添削してもったことで、自信をもって当日を迎えることができました。
実務をこなしながらの勉強は大切ですが、「不合格でした」と先輩に報告する姿を考えたくなかったので、”嫌な未来”から逃げるために、なんとか頑張れました。
身近に試験の合格者がいるなら、その人 (会社の先輩等) に大まかに見てもらい、ある程度固まった段階で、有料のサービスを利用して添削をしてもらいましょう。
「この論文でいいのかな?」と疑問をもったまま、試験に臨むより圧倒的にマシです・・・
他の人の論文を参考に、 自分なりに書いてみる
⇨フィードバックをもらい、ダメなところを直す
 ぜねた
ぜねた私は当時勤めていた会社が提供してくれた、論文の添削のサービスを利用しました
「同じようなサービスってないのか?」と探していたところ、見つけたのがコレです。
合格者合計 58,000名を搬出し18年間続く老舗。
実績のある第三者の添削を受けることで、 試験の当日に不安がなくなり自信をもって受験できます。
1級土木施工管理技士という1人前の技術者の証を手にしたい方は、申し込んでみてもよいのではないでしょうか?
実際に、会社の同僚が利用したので口コミは、コチラから
独学サポート事務局って口コミや評判良くて、実績もすごいけどどうなの?実際に利用した結果 【論文の代行は効果アリ】

さらに、具体的に私がやったことは、[一級土木施工管理技士の合格のために私がやった7つのこと 【合格体験記】]で詳しく書いて言います。
✅1回の受験で合格できた”秘密”を解説
1級土木に合格して一人前の技術者として認められるまでの、ストーリーを約7,000字のボリュームで執筆しています。
関連記事 一級土木施工管理技士の合格のために私がやった7つのこと 【合格体験記】

経験記述論文の書き方について、具体例を交えて解説しました。
1級土木施工管理技士の経験記述について、どんなことを書けばいいのか、どうやって勉強すればいいのか理解できたと思います。
・「工事名」「工事の内容」「工事現場における施工管理上のあなたの立場」は正しく書きましょう
・令和6年度以降は問題が変わっているので注意
・第三者からフィードバックをもらい、作文をブラッシュアップすべき
以上、1級土木施工管理技士の実地試験における経験記述について解説しました。
土木施工管理技士の技術検定試験に合格するためには、しっかりとした準備が必要不可欠です。私が合格できたのも、会社の同僚が合格できたのも事前の準備を欠かさなかったからです。
実際に私がどんなことをやって合格できたのか1つの記事にまとめましたので、最短距離で合格したい人は[一級土木施工管理技士の合格のために私がやった7つのこと 【合格体験記】]を参考に実践してみて下さい。

なお、土木施工管理技士の試験について、もっと効果的な対策を知りたいという方は私の公式LINEで特典としてプレミアム記事を公開しています。
・土木施工管理技士試験の勉強方法!1万字で徹底解説
・試験の勉強をする際に陥りがちな落とし穴3選
・経験記述論文の例文集5選
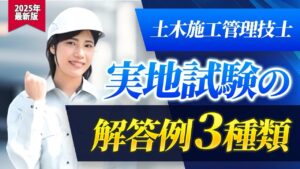
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
『つちとき』にコメントする