\ 公式LINE登録は完全無料 /
今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

 若手技術者
若手技術者盛土の作業ってどんな順番で進んでいくんですか!?
 ぜねた
ぜねた盛土の作業は、材料の搬入→敷き均し→締固めの3ステップです。
 若手技術者
若手技術者なるほど、どんな管理が必要ですか?
 ぜねた
ぜねた敷き均しの厚さと、締固め度等の品質の管理が必要です。
こんな疑問を解決します。
盛土の施工手順について
盛土の施工に必要な管理について
盛土の工事と環境への配慮について
この記事では、盛土の施工手順を解説します。
これを読めば盛土の施工手順や品質の管理方法が理解できます。
執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版
1級土木施工管理技士で元ゼネコンマンが、1級土木施工管理技士の試験でも良く出題される盛土の施工について解説します。
また、同じく1級土木施工管理技士の試験で進出問題である土量の変化率については、コチラの記事で詳しく解説しています。


 若手技術者
若手技術者盛土の作業の段取りには何が必要ですか!?
 ぜねた
ぜねたまずは、材料の搬入が必要です。
盛土の作業を始める前に、準備が必要です。
盛土を行う前に、盛土で使用する材料を準備し、どの位置にどのように施工を行うのか丁張をかけて示す必要があります。
また、盛土の施工を行うときの品質の目標を決め、その目標を達成できるような品質管理の計画を立てます。
というように、事前の準備に必要なことは3つありますが、まずは材料の手配から解説していきます。
 ぜねた
ぜねた材料がないと作業を始めることができません
高品質の盛土を構築するために、盛土に適した土とはどんな土なのか、詳しく見ていきましょう。

土は建設材料の中でも、安価で材料の性質が安定したものです。
盛土の材料には、施工が容易で、盛土の安定性を保ち、かつ有害な変形が生じ無いような材料を用いる必要があります。
これは1級土木施工管理技士の問題としてよく出題されるので理解しましょう。
 ぜねた
ぜねた実際のセクでは、現場で発生した土を使用して盛土を行うのが一般的
ですが、その中でもより高品質の構造物を構築するためにも、極力締固めが容易で強度ができる良い土を利用しましょう。
工事の施工を行う前には、現地で丁張をかけて構築する工事目的物を可視化しましょう。
「どの位置に」「どの高さで」構造物を構築するのか、現地で表すことができるのが丁張です。
X軸、Y軸、Z軸の3つの要素を現場で示すことができます。
 ぜねた
ぜねたコンクリート構造物でいうところの”墨”と同じです
土工事の作業で必要な丁張については、[土木工事における丁張のかけ方!丁張について元ゼネコンマンが徹底解説【若手技術者向け】]で詳しく解説しています。
✅門型、トンボのかけ方を解説
丁張のかけ方や、計算方法など具体的な計算法夫雄を交えて解説しているので、丁張を一人でかけられない人は必ず見てください。
関連記事 土木工事における丁張のかけ方!丁張について元ゼネコンマンが徹底解説【若手技術者向け】
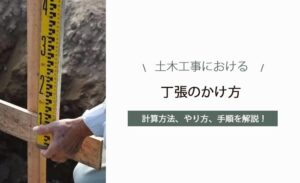
なお、盛土を施工するには、法丁張をかける必要があります。
法丁張の具体的なかけ方は本記事の内容からは外れてしまうため、[法面には法丁張!切土、盛土の丁張りのかけ方や高さの計算方法を元ゼネコンマンが解説!]で詳しく解説しています。
✅図解入りで法丁張のかけ方を解説
新人だったころに知りたかった情報を詰め込みました。「法面丁張のかけ方くらいしってるよ」って方こそ、自分が教えるつもりで復習として読んでもらえるとお嬉しいです。
関連記事 法面には法丁張!切土、盛土の丁張りのかけ方や高さの計算方法を元ゼネコンマンが解説!

高品質な盛土を構築するためには品質の管理が大切。
盛土の品質管理の最重要項目は、締固めの基準を満たしているかどうかです。
そのためには、発注者ごとに定められた品質管理の基準を事前に確認して、締固めの基準を満たすために重機と施工方法をしっかりと選定しましょう。
 ぜねた
ぜねた品質の基準は必ず事前に確認しましょう
具体例をあげると、(社)日本道路協会『道路土工-盛土工指針』では、路体及び路床における日常管理の基準値を以下のとおり定めています。
締固め度Dc=90%(路体)
95%(路床)
詳しい品質管理の基準については後程解説しますが、施工の前には品質管理の規定を確認しないことには、使用する機械を選定するといった準備ができません。
なので、事前に品質の管理規定を確認することはマストです。

 若手技術者
若手技術者よーし、土を搬入したからどんどん盛るぞー
 ぜねた
ぜねた待って待って、一度に敷き均すことができる高さは決まってます。
土は均一に敷き均しを行い、転圧を行うことで所定の強度と支持力を発揮することができます。
敷き均しの厚みのことを巻き出し厚とも言いますが、発注者によって巻き出し厚も決まっているので、よく確認しましょう。

現場では丁張をかけたり、構造物にマーキングを行ったり、することで巻き出し厚を管理します。
このようなテープが構造物についているのを見たことないですか!?
赤と白のテープなので、写真の撮影をした場合、一目で1層の厚みが確認できます。
測定用の丁張をかけるのに比べて、シールを貼るだけなの作業が容易です。
 ぜねた
ぜねた橋台まわりやボックスカルバートの周りの裏込め盛土に効果的です
1層ごとに写真をしっかり撮りましょう。

 若手技術者
若手技術者盛土の締固めって締固め度があればいいんじゃないんですか?
 ぜねた
ぜねた盛土の締固めは品質規定方式にも2つの種類があります。
大きく分けると、発注者が定める工法規定方式と受注者が決める品質規定方式がありますが、一般的には品質規定方式を使用します。
品質規定方式では、盛土の品質を管理する手法として、最大乾燥密度と最適含水比も用いた締固め度による管理が一般的です。
しかし、土質力学でも出て来るように、土は粘土と砂質土で性質が異なります。
そのため、管理手法も大きく分けて2種類あります。
せっかくなのでこの機会に一度確認しましょう。

盛土の品質管理では、締固め度Dcで管理するのが一般的です。
締固め度Dcとは
土の突き固め試験(JIS A 1210)のA-C法によって得られた最大乾燥密度を分母とし、分子を締め固めた材料の乾燥密度として百分率で割ったもの
締固め度(Dc)=現場密度/室内試験での最大乾燥密度×100%
国土交通省の道路工事で対象土が砂質土の場合の締固め度は以下の通りです。
| 工種 | 締固め度(Dc) |
|---|---|
| 路体 | 90%以上 |
| 路床 | 95%以上 |
施工を行った盛土が、この基準を満たしているのかどうかを現場で確認します。
実際に、現場で密度を確認する方法を現場密度試験といい、以下の方法で行うのが一般的です。
現場密度試験
・砂置換法
・RI法
詳しい試験方法については、[現場密度試験の砂置換法ってどんな試験?突砂法やRI法との違いも解説]で解説してます。
✅砂置換法の手順や方法を図解付きで解説
現場密度試験の突砂法やRI法との違いも解説しているので、土工事や舗装工事に従事する方は一度読んでおくことをオススメします。
関連記事 現場密度試験の砂置換法ってどんな試験?突砂法やRI法との違いも解説


この方法は①の方法が適用しにくい、自然含水比が高い粘土に対して適用される方法です。
 ぜねた
ぜねた関東では関東ロームを使った盛土などはこの手法で管理します。
締固めた土の湿潤密度及び含水量を測定し求めた空気間隙率(Va)および飽和度(Sr)が規格値を満たしているか確認します。
もちろんこの方法の適用が難しい場合は、①の方法で管理します。
国土交通省の道路工事で対象土が粘土の場合の規格値は以下の通りです。
| 工種 | 空気間隙率(Va) | 飽和度(Sr) |
|---|---|---|
| 路体 | 2%≦Va≦10 | 85%≦Sr≦95% |
| 路床 | 2%≦Va≦8 |

 若手技術者
若手技術者土地を大きく変える盛土って環境に良くないですよね・・・
 ぜねた
ぜねた一定規模以上の土地の形質の変更を行う場合は土壌汚染対策法の対象となります。
現在では、土地の形質の変更(3000㎡以上)を行う場合には、土壌汚染対策法に基づき工事着手30日前までに形質の変更を行う者による都道府県知事への届出が必要です。
また、3000㎡未満の広さの土地でも都道府県知事が指定した範囲での施工の場合、土壌汚染対策法の届け出が必要になります。

持続可能な社会の実現のためには、建設発生土の削減が課題となっています。
 ぜねた
ぜねた建設業の産業廃棄物は全産業の約2割を占めています
実際に、平成30年度の建設発生土搬出量は1億3263万m3に対して、平成24年度は1億4079万m3と5.85%減のほぼ横ばいです。
持続可能な社会の実現のためには、なるだけ場内で土を使うように受注者発注者一体となって、今後も廃棄物を減らす取り組みをしていきましょう。
盛土の施工手順について解説しました。
管理をしっかり行って高品質な盛土を造りましょう。
盛土の作業は、材料の搬入→敷均し→締固めの3ステップ
盛土は敷き均し厚と、品質(締固め度or空気間隙率)の管理が必要
建設発生土の抑制とCO2排出量の削減のために、できるだけ場内の土を使うようにしましょう。
以上、盛土の施工手順について解説しました。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!
『つちとき』にコメントする