\ 公式LINE登録は完全無料 /
今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中
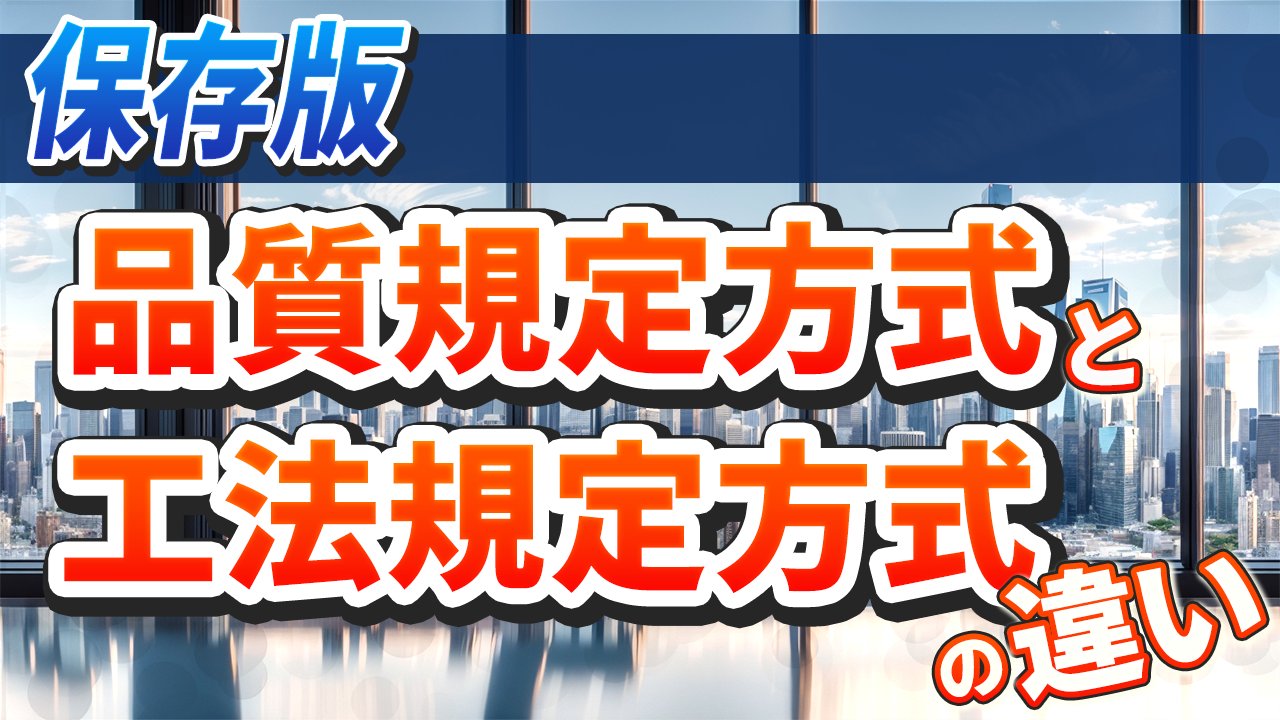
 若手技術者
若手技術者品質規定方式とは何ですか?
 ぜねた
ぜねた品質規程方式は管理規定の規格に収まるように、受注者が締固め方法を定める方式です
 若手技術者
若手技術者工法規定方式とは何ですか?
 ぜねた
ぜねた締固め機械の機種や、 締固め回数などを発注者の仕様書に明記して、品質規定とは逆に発注者が締固め方法を定める方式です
・品質規定方式って何?
・工法規定方式って何?
・具体的にはどんな風に管理するの?
こんな悩みを解決します。
品質規定方式の概要
品質規定方式の3つの管理手法
工法規定方式の概要と注意点
この記事では、盛土の管理手法である品質規定と工法規定について解説しています。
これを読み終えれば、品質規定方式と工法規定方式がどんな手法で、どのような違いがあるのか理解できます。
執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版
当サイトの運営者ぜねたの詳しいプロフィールは、コチラです。
なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。
YouTube
現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中
なお、土の締固めについては[土の締固めとは!?使用機械や締固まる理由を1級土木施工管理技士が徹底解説!]で詳しく解説してます。
✅締固めの施工手順や管理手法を解説
関連記事 土の締固めとは!?使用機械や締固まる理由を1級土木施工管理技士が徹底解説!

当サイトでは、現場監督の抱える悩みを解消するコンテンツを用意しているので、ぜひ参考にしてみて下さい。

 若手技術者
若手技術者品質規定方式とはどんな方法ですか?
 ぜねた
ぜねた締固め後の品質を仕様書に明記して、締固めの施工方法を受注者に委ねる方式です。
盛土の品質管理については、品質規程方式と工法規定方式の2方式があります。
品質規程方式は管理規定の規格に収まるように受注者が締固め方法が定めるもので、工法規定方式は発注者が締固め方法を定めるものです。
品質規程方式の代表的な管理方法以下のとおりです。
品質規程方式
・最大乾燥密度による管理
・空気間隙率、飽和度による管理
・強度特性、変形特性による管理
まず、 品質規程方式について解説します。
一番、ポピュラーに活用されているのが、 最大乾燥密度と最適含水比を用いた管理方法です。
現場で測定した密度から締固め度を算出して管理を行います。
 ぜねた
ぜねたDc 管理ともいわれます
砂質土で用いる管理方法で、盛土で使用する材料を 「土の締固め試験」を行い、最大乾燥密度p dmax と最適含水比 Wopt を求めます。
施工完了後、 現場の密度 pd を求め、
締固め度(%) = ρd/ρdmax
ρd:乾燥密度、ρdmax:最大乾燥密度
を計算し、規格を満たしていることを確認します。
なお現場密度の測定方法は、[現場密度試験の砂置換法ってどんな試験?突砂法やRI法との違いも解説]で詳しく解説しています。
✅現場密度試験における砂置換法について解説
砂置換法のやり方や道具だけでなく、突砂法やRI法との違いも解説しています。

締固めを行った土の空気間隙率または飽和度が一定の範囲内に収まるように規定する方法です。
乾燥密度による管理を行いにくい自然高い含水比の粘土について、用いられます。
空気間隙率 Va および飽和度 Sr は、現場で締固めた土の湿潤密度pt(g/cm3)および含水比w(%)を測定することで求めることができます。

Pw: 水の密度、Pd: 乾燥密度、Ps: 土粒子の密度
現場で測定し、この式により求めた空気間隙率および飽和度が規格を満たすことを確認します。
空気間隙率および飽和度の規格値は、 (社)日本道路協会 『盛土工指針』によると以下のとおりです。
管理規定
・空気間隙比 (Va) 10以下
・飽和度(Sr)85 以上
この両指標の具体的な使い分けは明記されておらず、 受注者の任意の方法で管理を行えます。
どちらの指標で管理した方が良いのかについては、
『高含水比粘性土を用いた高規格道路盛土の締固め管理と品質実態』という論文で詳しく記述されています。
この論文に書いてることを簡単にまとめると以下の通りです。
空気間隙率の管理をおこなうことで効率的に高品質の管理を行うことができる
 ぜねた
ぜねた実際はある一定の含水比以下であれば、 Sr管理の方が盛土の品質は向上します
しかし、日本で粘性土の盛土を行う場合、自然状態の含水比は高い傾向にあるため、空気間隙率の管理を行う方がより厳しい基準になり、盛土の品質向上につながります。
 ぜねた
ぜねた実際、 NEXCOの工事では飽和度の規定はなく、空気間隙率の規定しかありません
この方法は、 締め固めた土の強度・変形抵抗を貫入試験、 現場CBRなどで測定する方法です。
強度…平板載荷・CBR・コーン貫入試験 K値、CBR値、qc値
変形…プルフローリング
メリットとして、強度・変形の抵抗性であるため、直接盛土の共用性と関連するので試験が比較的容易です。
デメリットとしては、締固め後の水の浸入による強度の低下については確認を行うことができません。
浸水の影響が少ない材料に限定
| 向いている土質 | 向いていない土質 |
|---|---|
| 砂質土、礫質土 | 細粒土、粘性土 |
まだまだ、研究の余地がある方法であるため、 今後の適用範囲の拡大が期待されています。
ちなみに、土の締固めと関係が深いCBRについては、[CBRとは!?現場CBRと設計CBRと修正CBRの違いを1級土木施工管理技士が徹底解説]で詳しく解説してます。
✅現場CBR、設計CBR、修正CBRの違いを解説
140,975名が読んだ人気の記事です。
関連記事 CBRとは!?現場CBRと設計CBRと修正CBRの違いを1級土木施工管理技士が徹底解説

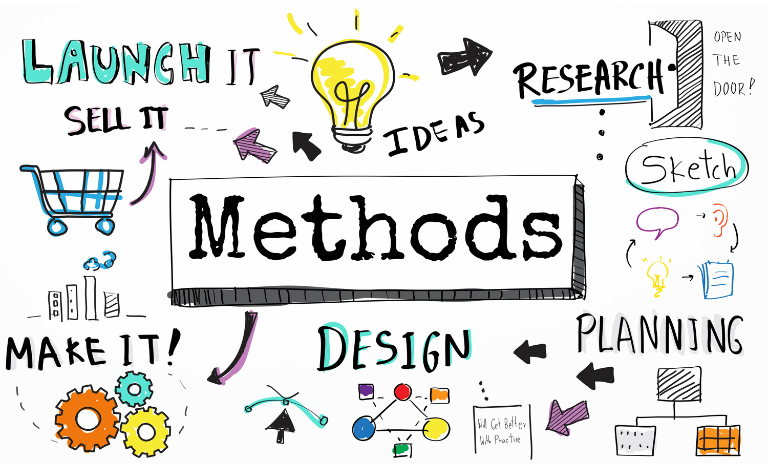
 若手技術者
若手技術者工法規定方式とは何ですか?
 ぜねた
ぜねた発注者が締固めの施工方法を仕様書で定める方式です
工法規定方式とは、 締固め機械の機種や、 締固め回数などを発注者の仕様書に明記して施工を行う方法です。
品質規定方式の適用が困難な岩塊(破砕された硬岩や中硬岩)に対して、適応されています。
タスクメーターと呼ばれる転圧機械の稼動時間を記録する装置又は、トータルステーション、GNSSなどの測量機器を使って転圧が行われたことを確認する方法です。
盛土の材料が土の含水比に影響されない岩塊や玉石などの施工に適しています。
岩塊
現場で発生するズリなどの大割の岩を直径30cm 程度に粉砕したもの
玉石
天然の石で丸みがあり直径14cm~18cmのもの
実際に、どのように管理していくのか、注意点を詳しく解説します。
締固めの施工方法を発注者が指定する工法規定ですが、 施工するにあたって注意点があります。
事前に試験施工を行い規定どおりに施工できるか要確認
工法規定により管理を行う場合、施工を行う前に試験施工を行い仕様書に定めた施工方法で管理を行うことができるのか、 事前に確認を行う必要があります。
試験施工で確認する項目
・敷均し厚
・ローラの種類、重量
・走行回数
敷き均し厚やローラの種類や走行回数を変えて、試験施工を行い、発注者から指定された工法で品質を確保することができるのか確認します。
試験施工で品質を満たしていることが確認できた場合、仕様書とおりの施工方法を採用します。
ちなみに、当初設計と土質や含水比が大きく異なる場合には、材料が変っている恐れがあるため、 施工方法を見直す必要があります。
 ぜねた
ぜねた一度、試験施工を行い締固めの方法を再度確認しましょう。
次に、工法規定の管理手法について詳しく解説します。
工法規定方式で用いられる管理手法は大きく2つです。
①タスクメータ・タコメータによる管理
②トータルステーション・GNSSによる管理
①の管理手法について解説します。
タスクメータ・タコメータによる管理は、 締固め機械に稼働時間を記録するタスクメータ・タコメータを取り付けて、 稼働時間を記録し管理する手法です。
実際の稼働時間 > 必要となる稼働時間
を確認します。
1日のあたりの必要締固め時間
= (搬入土量 × 必要締固め回数 ) /(仕上がり厚み× 締固め有効幅 × 走行速度 )
必要締固め回数: モデル施工により決定 (回)
仕上がり厚: モデル施工により決定 (m)
締固め有効幅 : 締固め有効幅=-0.25m (m)
走行速度: モデル施工で実施した速度(m/h)
引用:(社)日本道路協会 「道路土工 – 盛土工指針』 (平成22年度版)
次に、 ② の管理手法について解説します。
この式により求めた時間が1日当たりの必要締固め時間を上回っていることを確認します。
トータルステーション・GNSSによる管理は、 締固め機械の走行位置をTS (トータルステーション) やGNSS (人工衛星を用いた測位システム)でリアルタイムに計測する方法です。
転圧機械に取り付けたGNSSにより転圧機械の走行軌跡を可視化して、 転圧回数を管理します。
-1024x231.png)
国土交通省でも、GNSSを用いた管理手法を積極的に促しています。
さらに詳しく知りたい方は、『TS・GNSSを用いた盛土の締固め管理容量』(http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/kyoutuu/TS-GNSS-simekatame-H24.pdf) で詳しく解説しています。
 ぜねた
ぜねた近年は生産性の向上を目的にICTを用いた情報化施工がいろいろなところで行われています
ちなみに、盛土の施工手順については[盛土の施工手順!現場経験7年の元ゼネコンマンが徹底解説]で詳しく解説しています。
✅盛土の作業の流れを解説
盛土に使用する機械の選定基準も解説しているので、合理的な施工を行いたい方にはおすすめです。
関連記事盛土の施工手順!現場経験7年の元ゼネコンマンが徹底解説

盛土の管理である品質規定と工法規定について解説しました。
今一度、表にしてまとめます。
| 品質規定方式 | 工法規定方式 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 土木工事における盛土の管理において、仕様書などに発注者が定める品質を明記し、施工方法を受注者にゆだねる方式 | 締固め機械の機種、敷き均し厚さ、締固め回数などを仕様書で定め、この施工方法で品質を確保しようとする方式 ※試験施工が必要 | |
| 管理方法 | 締固めた土の乾燥密度と基準の締固め試験による最大乾燥密度との比(乾燥密度規定) | 一般的な管理手法 ①砂置換法 ②RI計器による方法 | 現場で乾燥密度を求めるための土質試験や、強度特性を求める試験が行いにくいような、岩塊や玉石などの粒径が大きい盛土材料の場合に適用。 タスクメーターによって転圧機械の稼動時間を記録し、転圧が行われたことを確認する。 近年では、締固めに使用するローラの走行する軌跡を、GNSSなどを用いてデータを取得し可視化して管理を行う手法も採用されている。 |
| 締固めた土の空気間隙率または飽和度(空気間隙率規定・飽和度規定) | 粘性土(高含水比)に使用 ①砂置換法 ②RI計器による方法 | ||
| 締固めた土の貫入抵抗、現場CBR、支持力など(強度特性、 変形特性規定) | 浸水の影響が少ない砂質土、礫質土に使用 ①平板載荷 ②CBR ③コーン貫入試験など | ||
最後まで、読んでくださってありがとうございました。
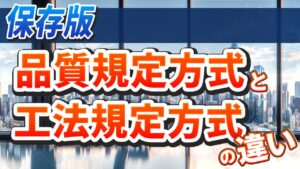
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
『つちとき』にコメントする