\ 公式LINE登録は完全無料 /
今すぐお友達になる公式LINE限定で、土木施工管理技士試験対策のプレミアム記事を公開中

 若手技術者
若手技術者土砂の掘削の場合の法面の安定勾配は!?
 ぜねた
ぜねた切土で土砂の場合は1:1.2が基本です。
 若手技術者
若手技術者なるほど。
では盛土の場合は!?
 ぜねた
ぜねた盛土の場合は1:1.5〜1.8が基本です。
こんな悩みを解決します。
切土法面の安定勾配
盛土法面の安定勾配
土工事について
この記事では、法面の安定勾配と土工事について解説しています。
これを読み終えれば、法面の安定勾配について盛土の場合も、切土の場合それぞれどんな勾配の法面にすればいいのかわかります。
執筆者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』著者

『つちとき』管理人|元準大手ゼネコン勤務|土木の現場監督7年|1級土木施工管理技士|【経験工種類】道路土工事、トンネル、PC上工、橋梁下部工|書籍『仕組み図解 土木工事が一番わかる』出版
1級土木施工管理技士の元ゼネコンマンが法面の安定勾配と、土工事の基本的な部分について解説します。
この記事は、(公社)日本道路協会『道路土工-切土工・斜面安定工指針』『道路土工-盛土工指針(平成22年度版)』を元に執筆しています。
なお、YouTubeでも土木工学や土木施工管理技士に関する情報を発信しています。
YouTube
現場で11年間働いて身につけた最新のノウハウを動画で公開中
また、法面の安定勾配だけでなく、土木工事に関する丁張について知りたい方は[土木工事における丁張のかけ方!丁張について元ゼネコンマンが徹底解説【若手技術者向け】]で詳しく解説しています。
✅土木工事における丁張のかけ方や計算方法、事前の準備について解説してます。
何もしらない新人だったときに知りたかった”丁張をかけるために必要な知識”をすべて書いています。
関連記事 土木工事における丁張のかけ方!丁張について元ゼネコンマンが徹底解説【若手技術者向け】
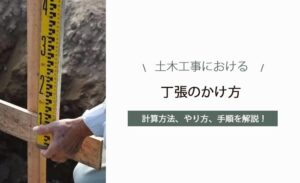
なお、勾配の表記方法について自信がない方は[勾配の計算方法は?パーセントって、角度にすると何度なの?]という記事で詳しく解説しています
✅角度とパーセント、比率の計算方法を解説
関連記事 勾配の計算方法は?パーセントって、角度にすると何度なの?


 若手技術者
若手技術者切土法面ってどれくらいが安定勾配なんですか?
 ぜねた
ぜねた土砂の場合は1:1.2(イチワリニブ)が一般的です。
 若手技術者
若手技術者硬岩の場合は?
 ぜねた
ぜねた硬岩の場合は1:0.3〜0.8(サンブ~ハチブ)です。
切土法面の安定勾配は、切土の高さと地山の土質によって異なります。
(公社)日本道路協会『道路土工–切土工・斜面安定工指針』に標準的な法面の安定勾配に関する記述があるので、詳しく紹介します。
地山の土質と、切土の高さ、勾配をまとめた表がこちらです。
| 地山の土質 | 切土高 | 勾配 |
|---|---|---|
| 硬岩 | 1:0.3~1:0.8 | |
| 軟岩 | 1:0.5~1:1.2 | |
| 砂 | 1:1.5~ | |
| 砂質土(密実なもの) | 5m以下 | 1:0.8~1:1.0 |
| 〃 | 5~10m | 1:1.0~1:1.2 |
| 砂質土(密実でないもの) | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 |
| 〃 | 5~10m | 1:1.2~1:1.5 |
| 砂利または岩塊混じり砂質土(密実なもの、または粒度分布のよいもの) | 10m以下 | 1:0.8~1:1.0 |
| 〃 | 10~15m | 1:1.0~1:1.2 |
| 砂利または岩塊混じり砂質土(密実でないもの、または粒度分布の悪いもの) | 10m以下 | 1:1.0~1:1.2 |
| 〃 | 10~15m | 1:1.2~1:1.5 |
| 粘性土 | 10m以下 | 1:0.8~1:1.2 |
| 岩塊または玉石混じりの粘性土 | 5m以下 | 1:1.0~1:1.2 |
| 〃 | 5~10m | 1:1.2~1:1.5 |
よく締め固まった土質ほど急な勾配で、緩い地盤ほど勾配をねかせる必要があります。
法面の勾配については、安衛則でも法面の安定勾配について定めがあります。
しかし、安衛則の場合は重機を用いない「手掘りの場合」の勾配です。
| 地山の種類 | 掘削面の高さ | 勾配 |
|---|---|---|
| 岩盤または堅い粘土からなる地山 | 5m未満 | 90° |
| 〃 | 5m以上 | 75° |
| その他の地山 | 2m未満 | 90° |
| 〃 | 2m以上5m未満 | 75° |
| 〃 | 5m以上 | 60° |

 若手技術者
若手技術者盛土法面の安定勾配はいくつですか!?
 ぜねた
ぜねた盛土の場合は1:1.5〜1.8が一般的です。
 若手技術者
若手技術者根拠となる書籍ってありますか?
 ぜねた
ぜねた『盛土工指針』に盛土法面に関する記述があるので紹介します
(公社)日本道路協会『道路土工-盛土工指針』では地山の土質によって異なりますが、盛土法面の安定勾配は1:1.5〜1.8と定められてます。
| 盛土材料 | 盛土高さ(m) | 勾配 |
|---|---|---|
| 粒度の良い砂(S)、礫及び細粒分混じり礫(G) | 5m以下 | 1:1.5~1:1.8 |
| 〃 | 5m~15m | 1:1.8~1:2.0 |
| 粒度の悪い砂(SG) | 10m以下 | 1:1.8~1:2.0 |
| 岩塊(ずりを含む) | 10m以下 | 1:1.5~1:1.8 |
| 〃 | 10~20m | 1:1.8~1:2.0 |
| 砂質土(SF)、硬い粘質土、硬い粘土 | 5m以下 | 1:1.5~1:1.8 |
| 〃 | 5~10m | 1:1.8~1:2.0 |
| 火山灰質粘性土(V) | 5m以下 | 1:1.8~1:2.0 |
安定した高品質な盛土を作るためにも、しっかりと勾配を守った盛土を構築しましょう。
なお、土の締固めについては、[土の締固めとは!?使用機械や締固まる理由を1級土木施工管理技士が徹底解説!]で詳しく解説してます。
✅土の締固めの原理や締固めに使用する機械を紹介しています。
既往の研究に基づいた適切な機械選定について解説しているので、効率的な締固め作業ができて無駄な作業を減らすことができます。
関連記事 土の締固めとは!?使用機械や締固まる理由を1級土木施工管理技士が徹底解説!


 若手技術者
若手技術者法面の安定勾配もわかったし施工もばっちりだ
 ぜねた
ぜねた掘削作業は危険が伴いますので、十分に気を付けてください
最後に施工時における注意点を確認しましょう。
土工事の施工における品質と安全に関する注意点を詳しく解説します。
土工事においては、特に雨水や地下水の処理が大切です。
なお、土工事については[土工事とは?一級土木施工管理技士が徹底解説]で詳しく解説しています。
✅土工事で使う機械や管理方法について解説しています。
土工事に使う機械や施工方法や施工の管理方法など、学びたい方はこの機会にサクッと勉強してみることをおすすめします。
関連記事 土工事とは?一級土木施工管理技士が徹底解

盛土を施工する場合の注意点は、以下の2点です。
それぞれ詳しく解説します。
まず1点目は切土と同様に排水処理が重要です。
 ぜねた
ぜねた盛土の作業で問題がおこる原因は、ほとんどが水です
その日の作業終了時には必ず転圧を行い、表面の排水を良好にし、盛土内に雨水が浸透しないとようにします。
ちなみに、盛土については[盛土とは!?元ゼネコンマンの1級土木施工管理技士が解説]で詳しく解説しています。
✅盛土で使う材料の特徴や品質管理について解説してます。
盛土の材料についてや、盛土の管理方法について執筆しているので、土を扱う現場に従事される方は必見の内容です。
「そんな知ってるよ」って方こそ、復習ついでに確認してみて下さい。
関連記事 盛土とは!?元ゼネコンマンの1級土木施工管理技士が解説
2点目として、切盛境では特に排水処理と段切りをおこない高品質な盛土をつくりましょう。
盛土の場合は地山と盛土の接続部に段差が生じやすく、地震や雨の際にすべり破壊が生じやすい傾向にあります。
 ぜねた
ぜねたそのためにも”段切り”の施工が大切です。
段切り
1:4より急な勾配の地盤上に盛土を行う場合に、滑動防止のため階段状に地盤を削ること
土砂地盤における段切りの標準的な仕様の目安は最小高さ0.5m、最小幅1.0mです。
また、盛土の施工手順については[盛土の施工手順!現場経験7年の元ゼネコンマンが徹底解説]で詳しく解説しています。
✅盛土の作業手順や関係法令について解説してます。
土木施工管理技士の試験でよく出題される盛土の施工について、詳しく解説しています。
関連記事 盛土の施工手順!現場経験7年の元ゼネコンマンが徹底解説

土工事や造成の現場では切土や盛土の法面を造る作業は必ずありますよね。
建設業において崩壊・倒壊事故は多く発生しています。
危険な作業であることをしっかりと頭に入れて、安定した掘削や法面の形成に努めていきましょう。
土砂で切土の場合は1:1.2が一般的
土砂で盛土の場合は1:1.5〜1.8が一般的
施工の際には雨水の処理に注意すること
以上、法面の安定勾配について開設しました。
施工管理技士の受験を考えている方は、「独学サポート事務局って口コミや評判良くて、実績もすごいけどどうなの?実際に利用した結果 【論文の代行は効果アリ】」を参考にしてみてください。
施工管理技士の資格は国家資格なので、 1人前の技術者の証になります。
私の同僚はこのサービスを利用して、 1度落ちた実地試験を翌年合格しました。
独学で勉強している人にはオススメのサービスです。

参考書籍
『道路土工ー切土工・斜面安定工指針 平成21年度版』
この記事が気に入ったら
フォローしてね!
『つちとき』にコメントする